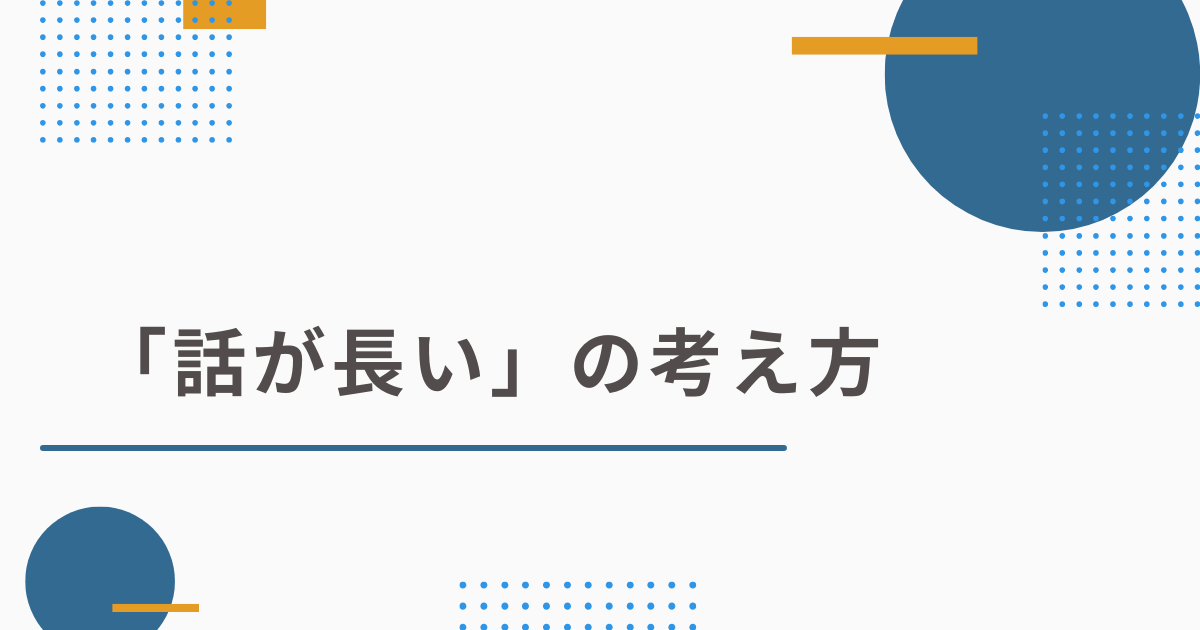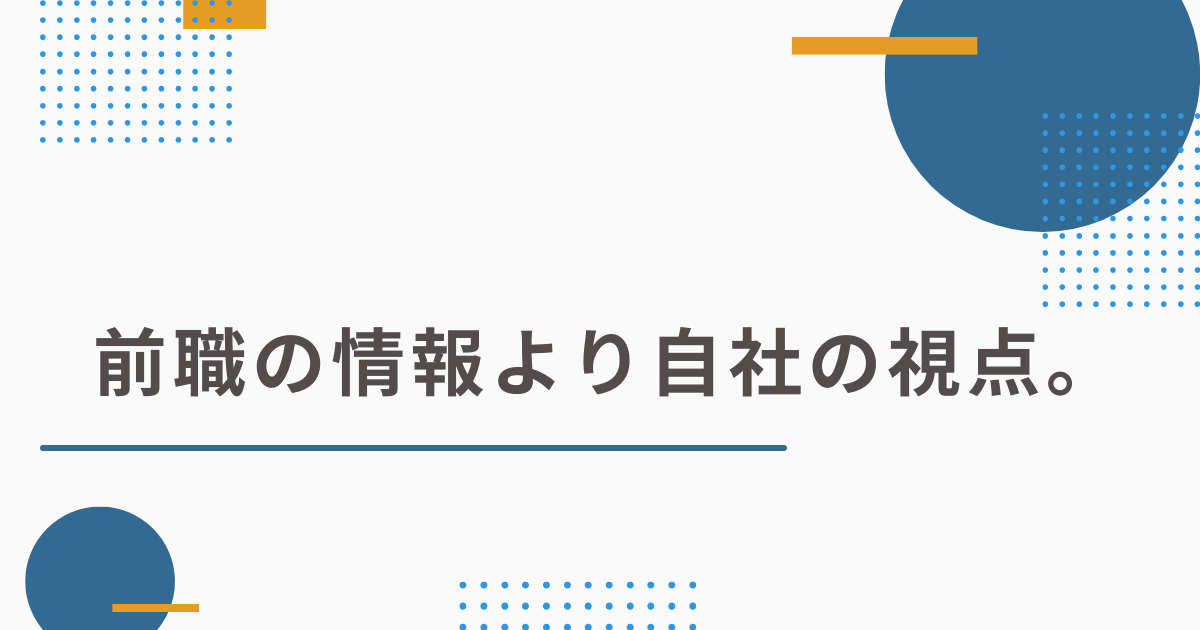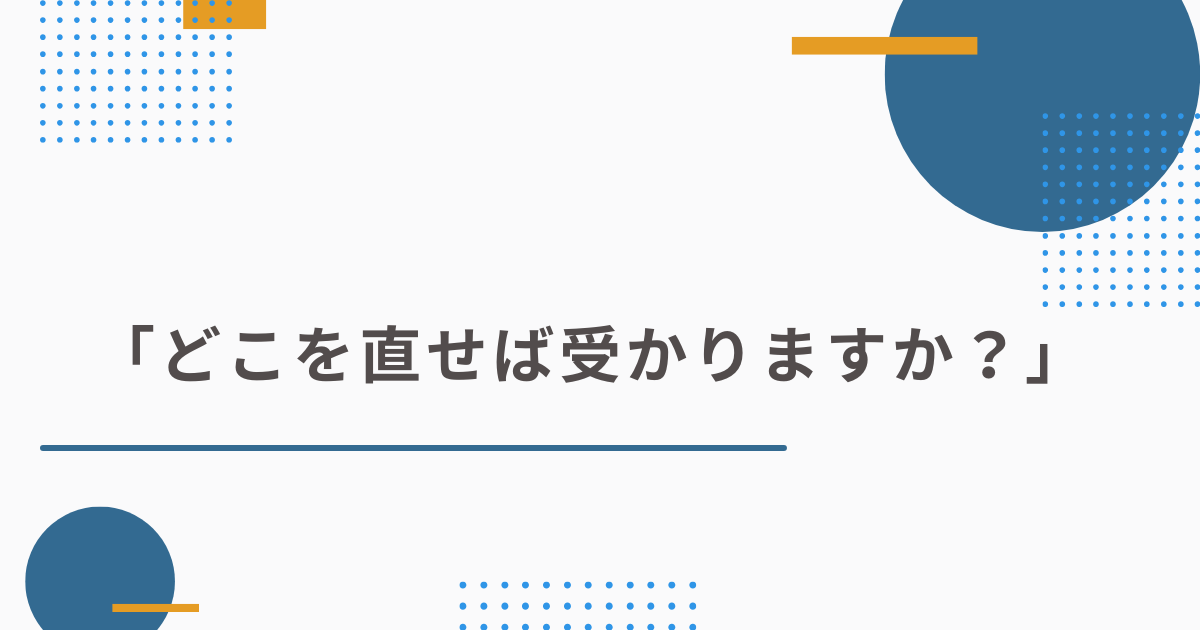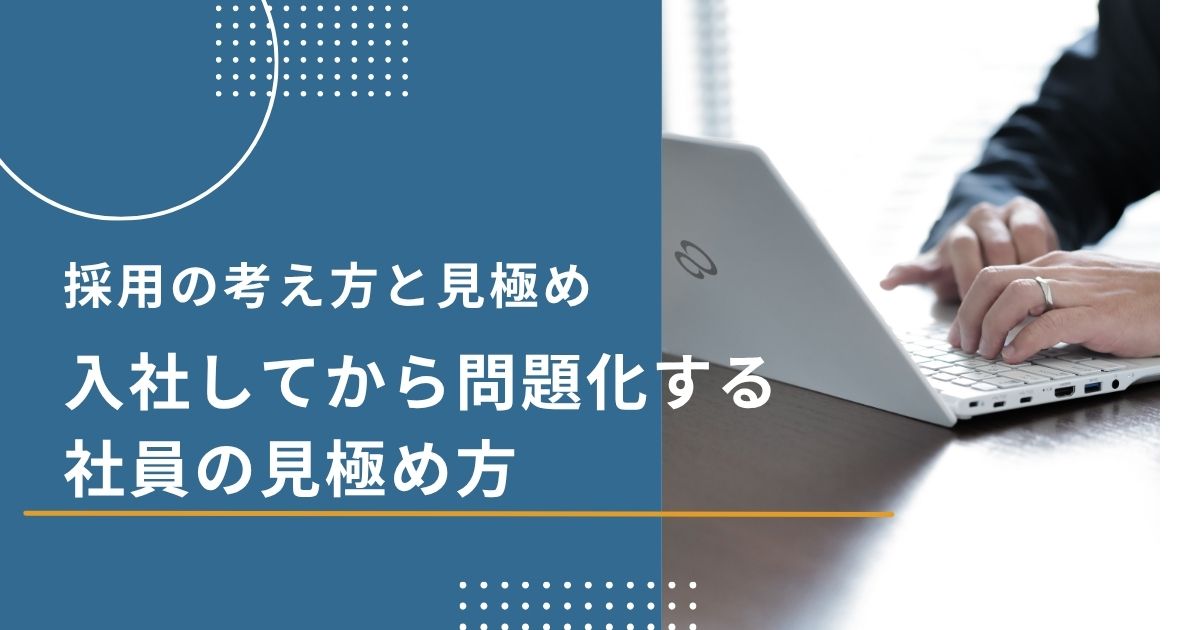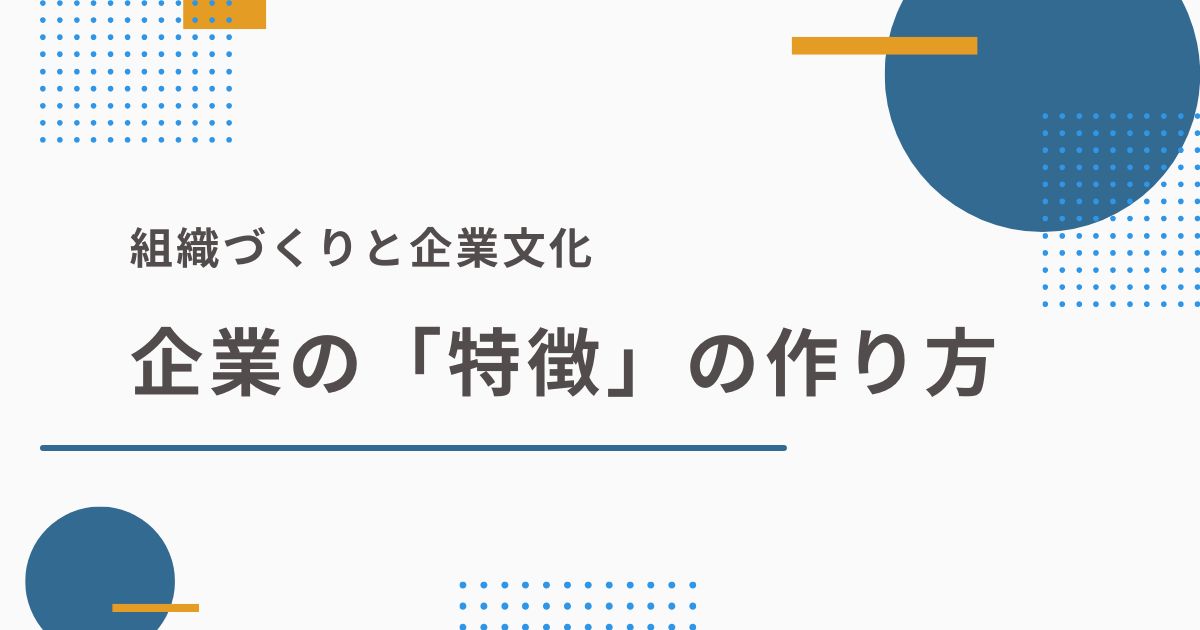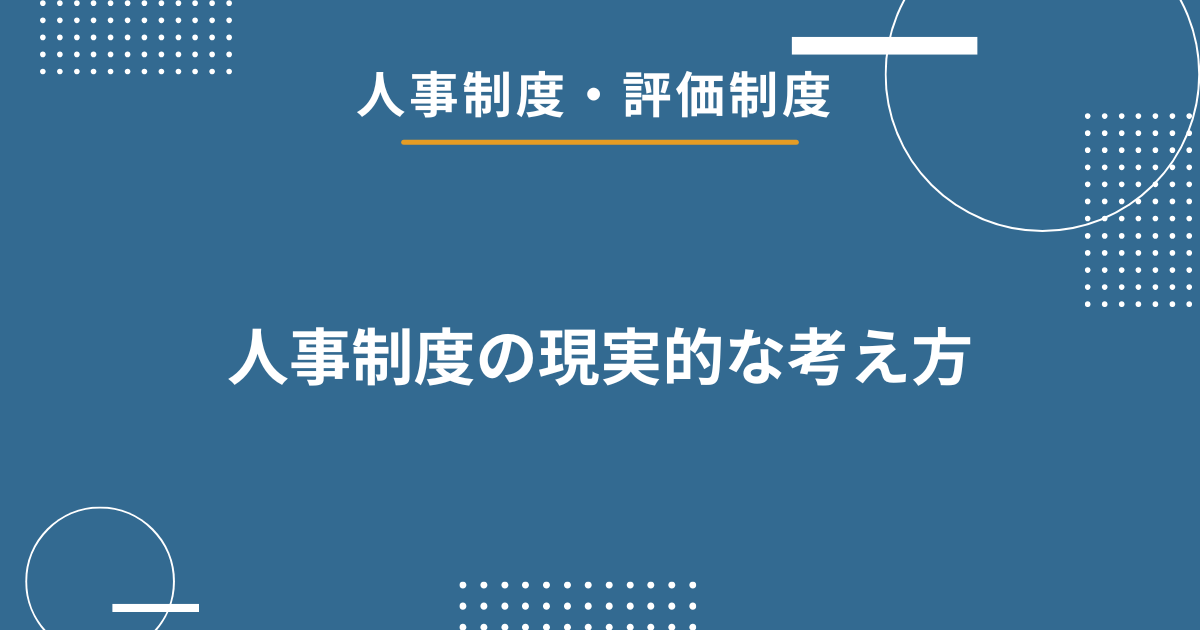1. 「話が長い」場合の4つのケース
始めに。自分のことを棚に上げて図々しく書きますが、世の中は「話の長い人」が一定数います。
採用においても、面接の場で話が長いな、と感じる場合、どのように考えていったらよいでしょうか。
まず、「話が長い」というのは、面接官としてはキャッチしやすく、重要な情報の一つです。最初の自己紹介など、緊張状態で話が長いが、少し落ち着いてきて話の長さが気にならなくなるのであれば、無理には特徴として取らなくても良いですが、終始話が長い場合は、「話が長い」と判断します
こういう話をすると、「どれくらい話したら「話が長い」と判断したら良いでしょうか?」と質問を頂くのですが、こちらが聞きたいことではない余計な話が多いな、回りくどくて長いな、と思うことが複数回あれば、話が長いと判断して良いでしょう。
では、話が長い場合、どのような人物像の可能性があるかというと、
- 目標設定が出来ない
結論を決めて、その目標に向かって話さず、思いついたことをだらだらと話している場合、目標設定が出来ない可能性があります。
- 情報の取捨選択が出来ない
伝えるのにあたり、必要のない情報も含めて話をするため、話が長くなります。こういう場合、情報の取捨選択が苦手で、重要度がわからず、優先順位付けが出来ない可能性があります。
- 故意にごまかす
はっきりと伝えたくない、ごまかしたい内容など煙にまくように、不要な内容を散りばめ、名言を避ける、心理的防衛が高い可能性があります。
- 自己顕示欲
長く話すことで、自分がデキるように見せたい、頭が良いように思われたいなどの心理から話が長くなって、自己顕示欲が高い可能性があります。
概ね、この4つのどれかに当てはまる場合が多いです。
2. 「4つのケース」への絞り込み方
では、どうやって4つのどれかを判断するかは、話が長いという情報だけでは判断できず、その他の情報が必要となります。
例えば、話が長いという情報に加え
・長く話した上に「何の話でしたっけ?」と、結論がどこかに行ってしまう場合、1の「目標設定が出来ない」ケースの可能性が高まります。
・今までのキャリアや業務で意思決定を避けてきている場合、2の「優先順位付けが苦手」なケースの可能性が高まります。
・質問されることに不快な表情をしたり、語気が強まるなど「面接者が質問しづらい」と感じる場合、3の「故意にごまかす」ケースの可能性が高まります。
・流行りの横文字を多用したり、必要以上に難しい言葉が使われる場合、4の「自己顕示欲が高い」ケースの可能性が高まります。
3. 「4つのケース」の採用判断
以上のように、4つのどれかの可能性が高いとなった場合、では採用の判断としてはどのように考えて行ったら良いでしょうか。
まず、1.2と3.4は大きく違うポイントがあります。
1.2は能力的な要素が課題になってくるのに対し、3.4は人格的な要素が課題になってきます。
1.2は、能力的な部分として、自由度が高い環境で働くと、目標が設定できないため、企業の行くべき目標と違う明後日の方向に進んでしまったり、優先順位がつけられないため、非効率で無駄が多く生産性が低いアウトプットとなりがちです。そのため、目標設定と行動を制限する必要があります。反面、言われたことには前向きに取り組んでくれるのであれば、仕事内容によって採用の可能性が出てきます。例えば、工場などの現場作業など、作業が明確化されているのであれば、活躍してもらえる可能性があります。
ただし、現場作業を熱心にこなし、仕事を身に着け活躍しているからといって、リーダーなどの役職にあげる場合、仕事の自由度が増し、急激にリスクが表面化しやすくなるため、仕事の範囲を拡げるのは慎重に行う必要があります。
3.4の方について、まず特に気にしなければいけないのは3の「故意にごまかす」場合です。当社が面接に同席させて頂く場合、3の方については、状況や程度にもよりますが、NGとされることをお勧めしています。
選考を1つの業務と考えた場合、質問という会社からのミッションに対し、聞かれたことに答えるというアクションを行わない、つまり指示に従っていない、取り組んでいないと言えるからです。当然、教育研修においても「受け入れない」ため、効果は薄く入社後に変わる可能性は低いです。
そして、入社後社内で大きく問題となる可能性が高いため、経験などがあったとしても避けた方が良いと思います。
最後に4の方ですが、今回の4つの場合分けの中では最も判断が難しいです。自己顕示欲というのは、組織のためではなく、自己のために動くという意味では大きなリスクです。
ただし、文字通り「欲」というのはエネルギー源の1つとなるものです。資本主義自体が欲をベースにしているので、ビジネスのパワーとして欲というのは時にプラスとして働くものでもあり、組織として上手くいかせるのであれば採用の可能性はあります。
ただし、同じ欲でも「達成欲」「貢献欲」「成果欲」などと比べ、組織としては扱いにくい欲の一つでもあるので、慎重に判断をした方が良いことは間違いありません。
と・・・・・ここまで書いてきて大変お恥ずかしいのですが、自分も昔に比べれば制御方法はわかってきたとはいえ、若かりし頃は大変自己顕示欲にまみれており、そんな過去を棚に上げて書かせて頂いております(恥)
自分は過去にとても有難い出会いがあり、自分を制御し、向かう方向性を組織と合わせる術を教えてもらい、徐々に体得できたことで、後天的に何とかしてきた経験があります。そういう意味では、自己顕示欲の高い場合でも、自らのリスクや課題を受け入れ、修正しようという意欲のある方であれば、可能性はあるのではないでしょうか。
以上、話しが長い、というテーマについて書かせて頂きました。実際には、様々な他の要素ともつながっているため、一概に決めつけることは出来ませんが、1つの重要な情報となることは間違いありません。