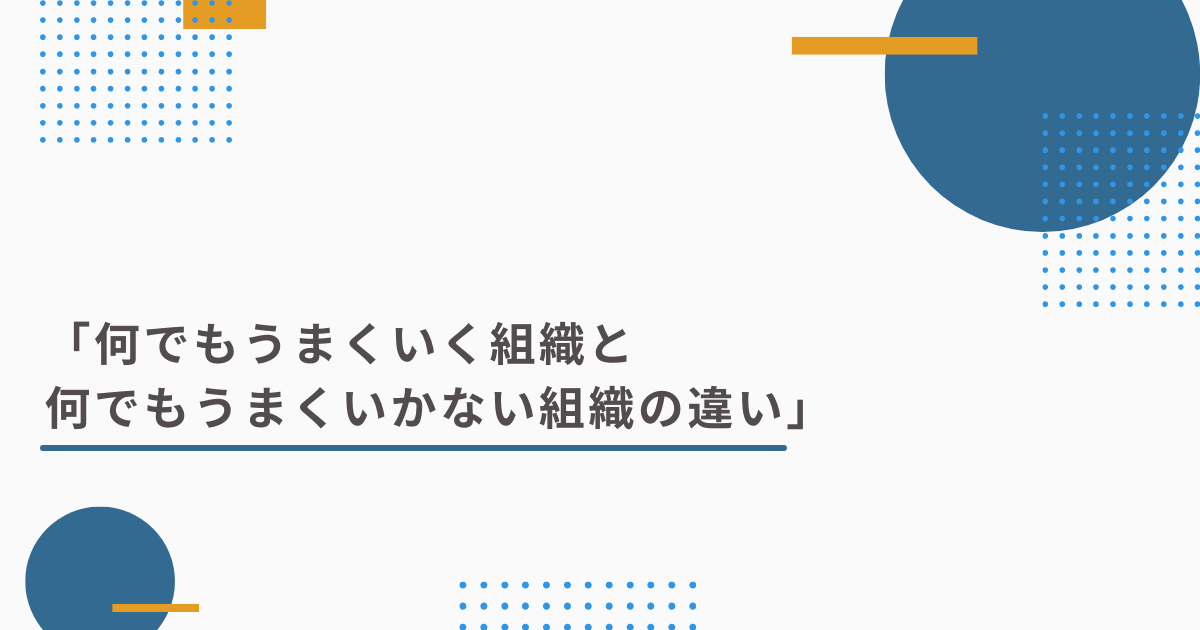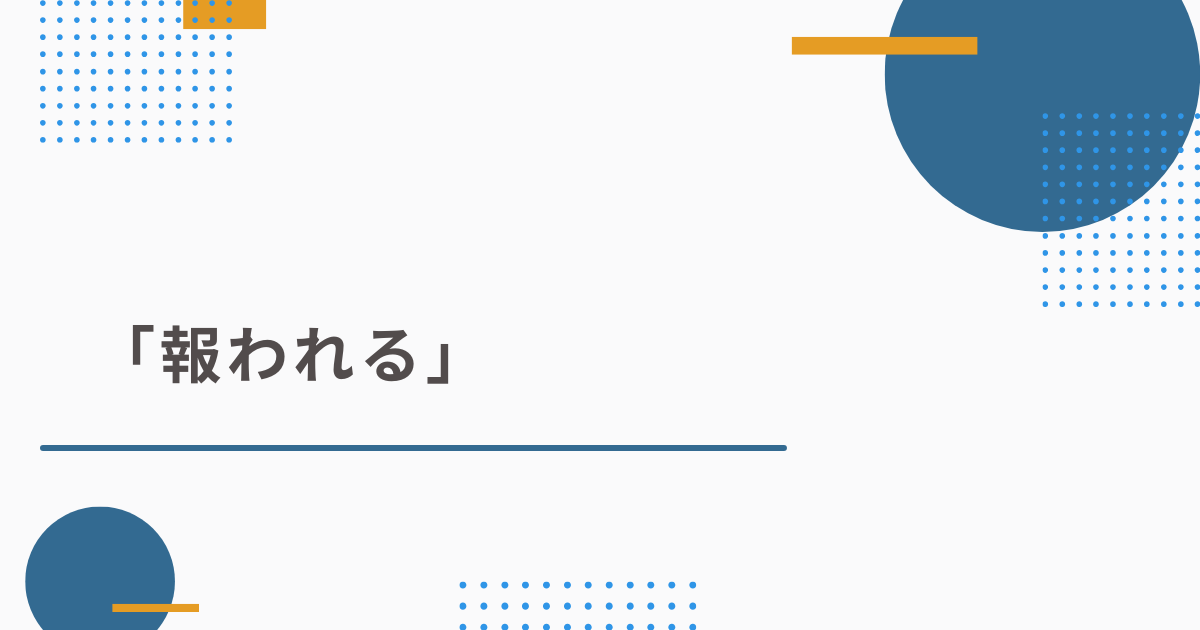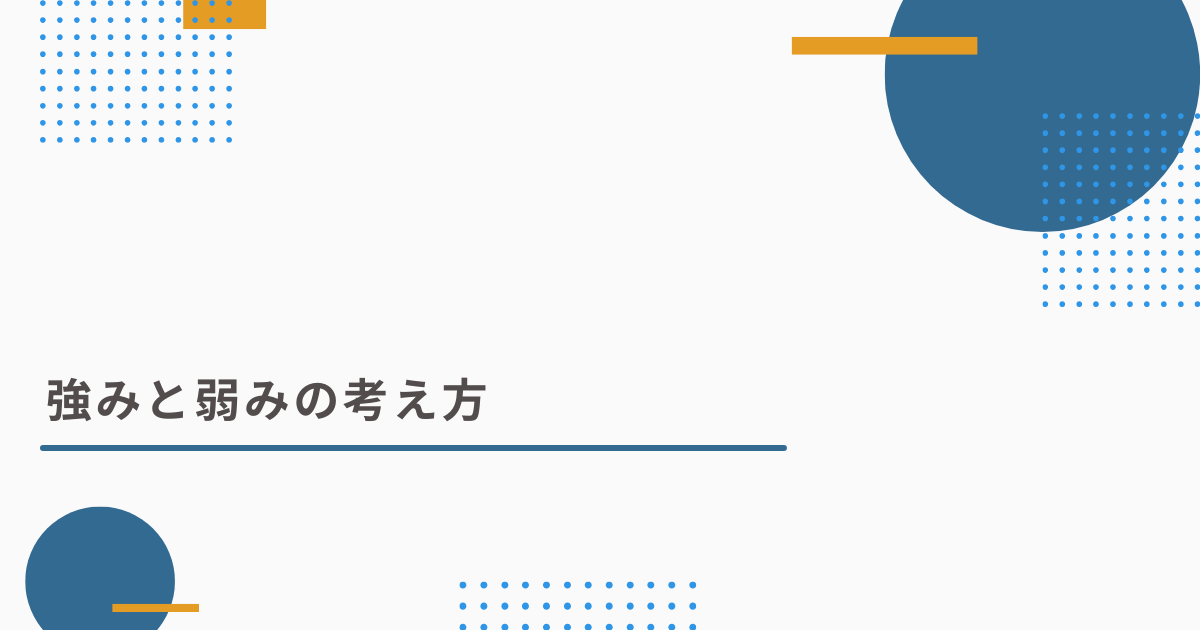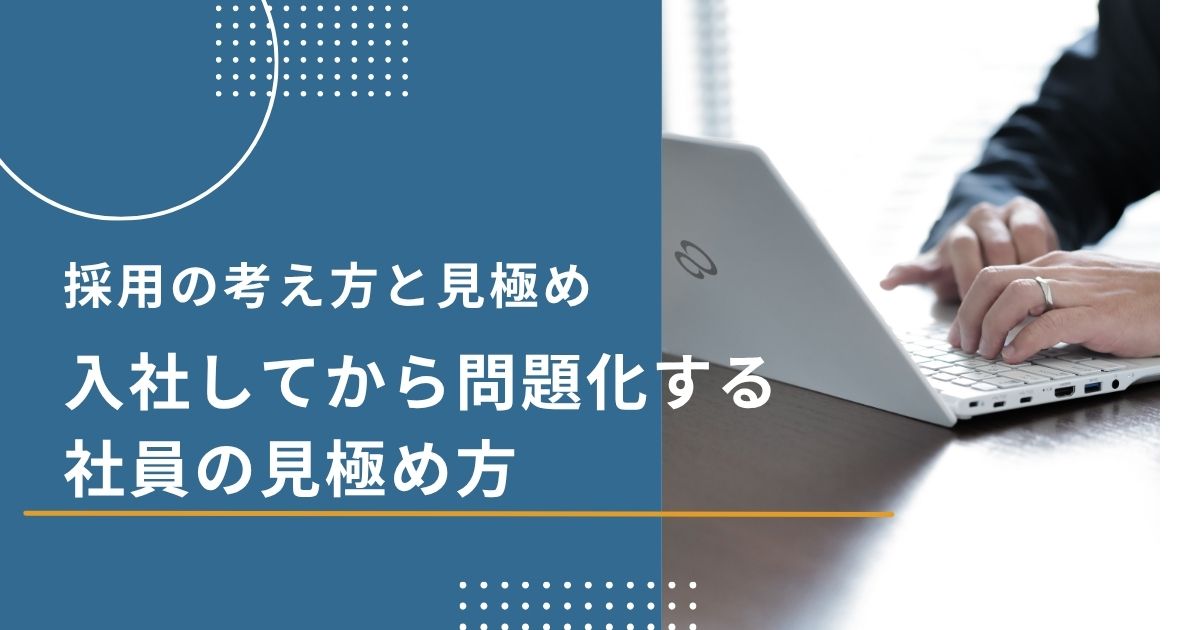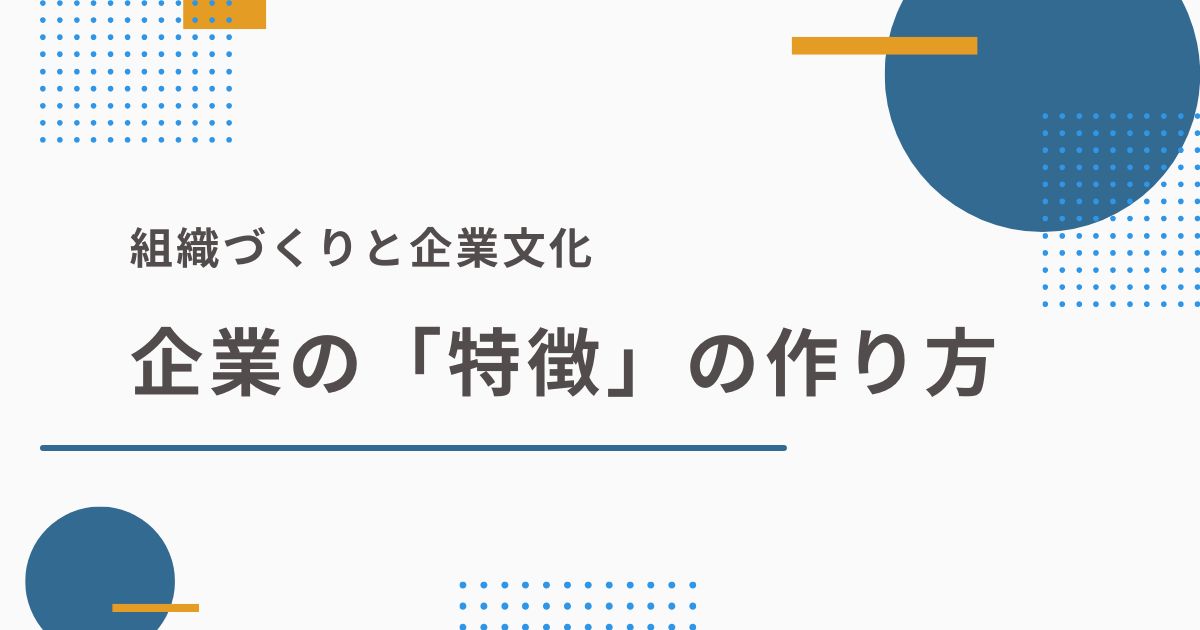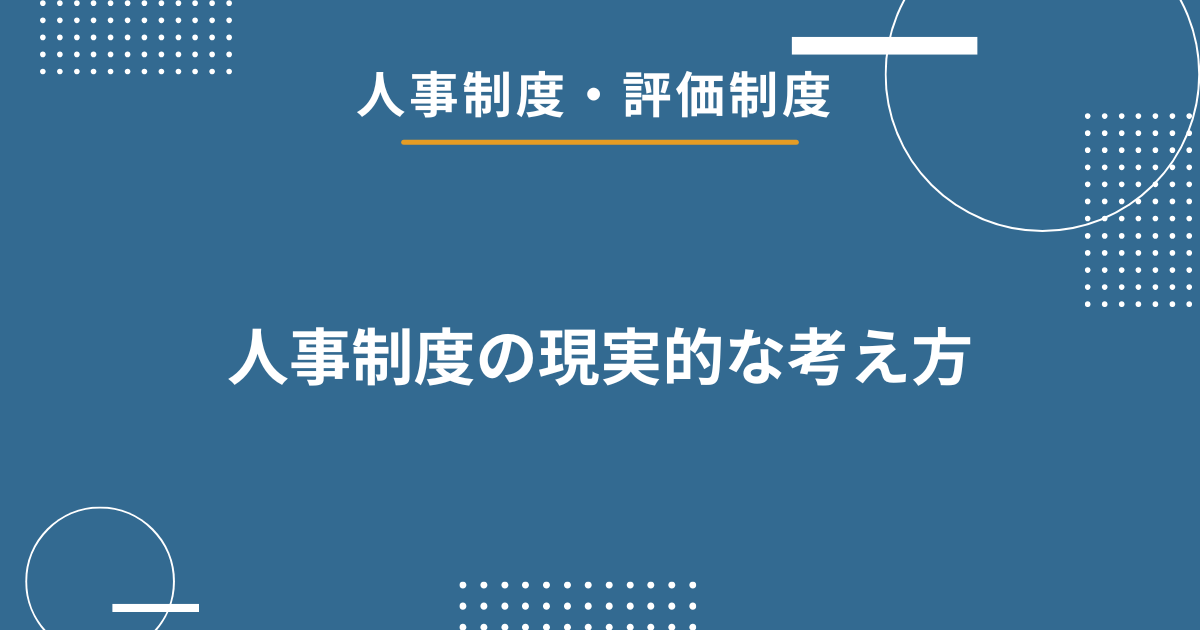1. 何でもうまくいく組織と何でもうまくいかない組織の違い
私は、サラリーマン時代、社内のシステム管理者(とか、品質管理とか、工場とか)を兼任していたことがあり、社内のネットワーク構築や、新しいシステムの導入を行っていました。
ある期間に4つほど新しいシステムを導入して、社内の効率化や情報共有、セキュリティの強化などを行いました。こういうシステムを導入しているときに、取引の業者さんから言われるのが、
「システムを入れるときは社内の仕組みを変えるため、反対意見が多く、とても苦労したり、そこで頓挫して失敗するケースが多い。御社も大変ですよね。」
という話。
でも、こちらの会社では、組織変革を進めた結果、新しい仕組みを入れるにあたって、組織の反対で苦労することは全くありませんでした。
「こういう意図があって、情報共有がしたいから、新しい仕組みを入れたい」というと、反対よりも、むしろ早くやってくれと逆に叱られる場合があったり、必要性を説明すると、すぐに受け入れて使ってくれます。
もちろんこちらも会社のためになると思って導入していますし、受け入れやすいように進めていきますが、結局上手く行かない組織は「とにかく反対」「反対のための反対」になってしまいます。これでは何をやってもうまくいきません。
そのため、組織変革の基本は、「反対する人」をあの手この手で減らしていき、「受け入れてくれる人」の割合を増やし、パワーバランスを変えることです(パワーバランスについてはまた別の機会に)。
反対する人が減り、新しいことを受け入れやすい組織になれば、導入にあたって反対されて頓挫することはまずありませんし、そこで苦労することはありません。もちろん、実際の現場での使用に合わせて運用に載せていくところで工夫するところでは苦労しますし、アイディア出しに苦しみますが、それは建設的な悩みだと言えます。
他のことも同様です。
例えば新しい社員が入るときでも「入れてくれてありがとう!」と部署からは感謝され丁寧に受け入れてくれるので、新入社員が定着しやすい。お客さんの要望にも「いやぁ、厳しいねぇ・・。でもお客さんも困っているよね?じゃあこうしてみようか?」となって、お客様の満足度も上がりリピートにつながる。
結局、受け入れやすい組織になればなんでもうまくいきますし、反対ばかりしている組織は何をやってもうまくいきません。
単純ですが、どんな優れたシステムやソフトでも組織が受け入れなければ、結局無駄になってしまうので、まずは「受け入れやすい組織」作りを進める方が優先です。