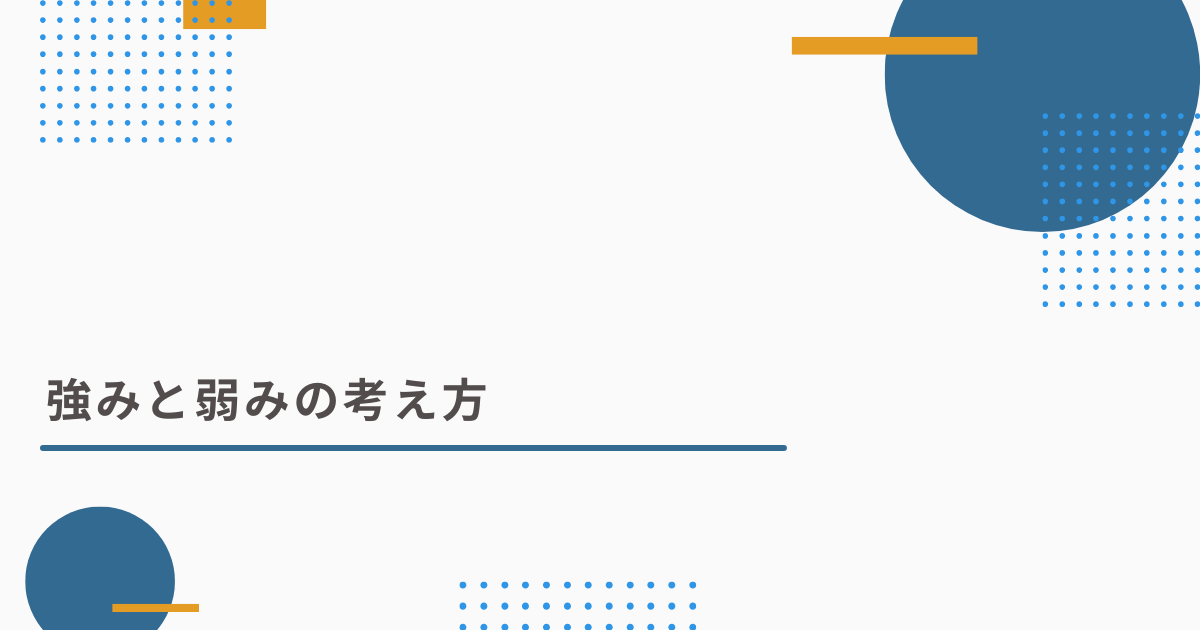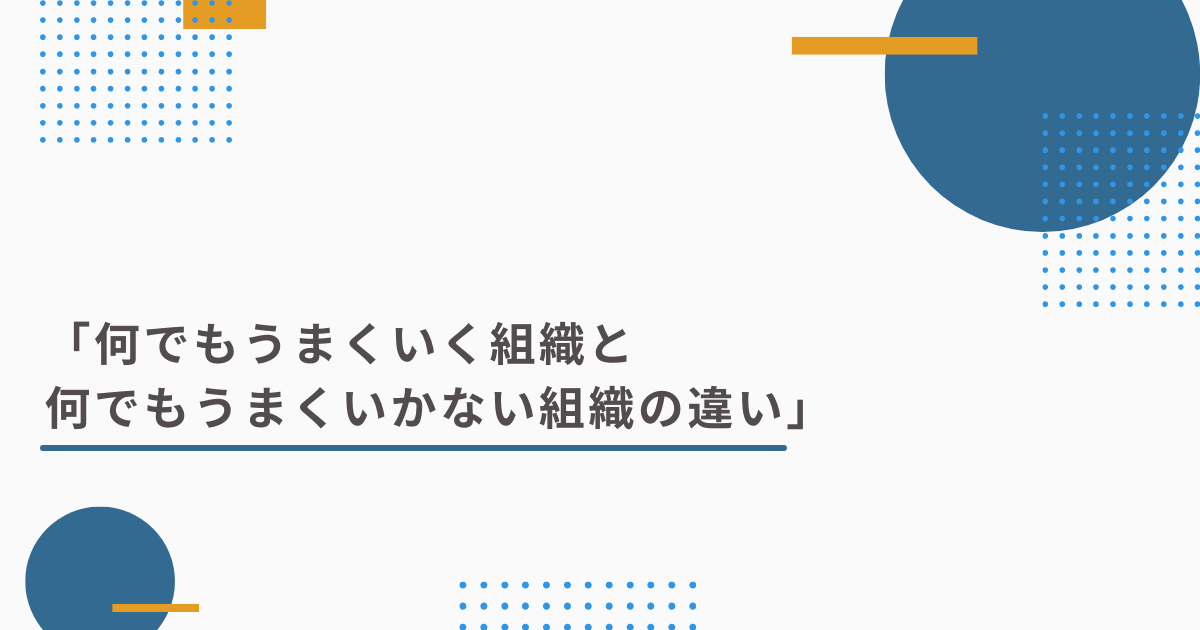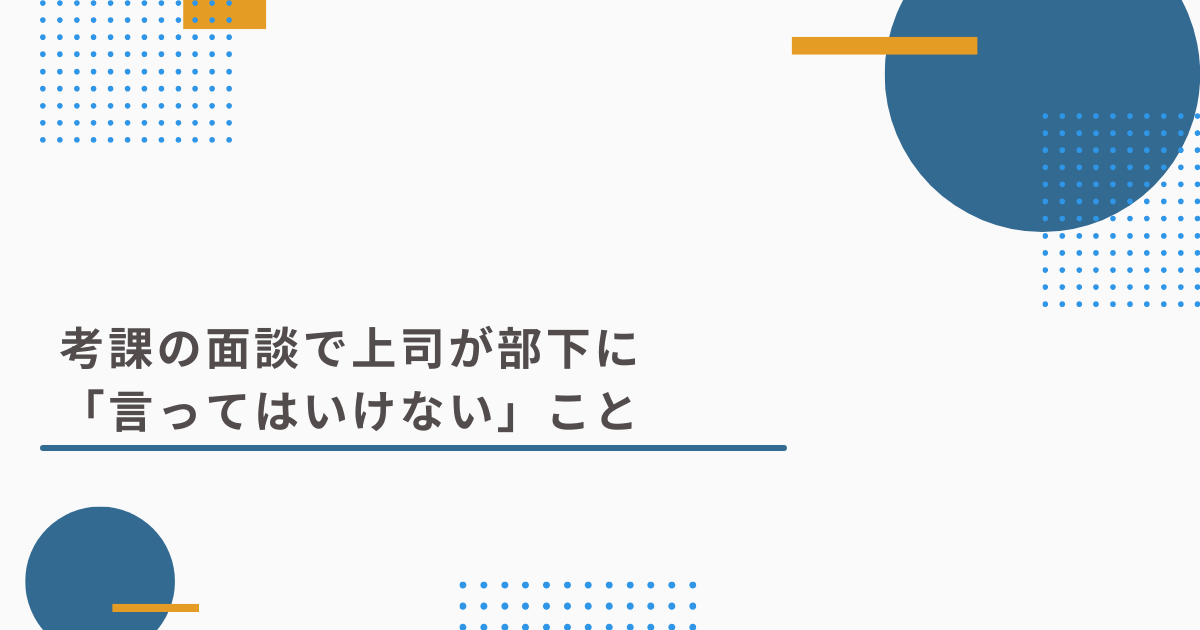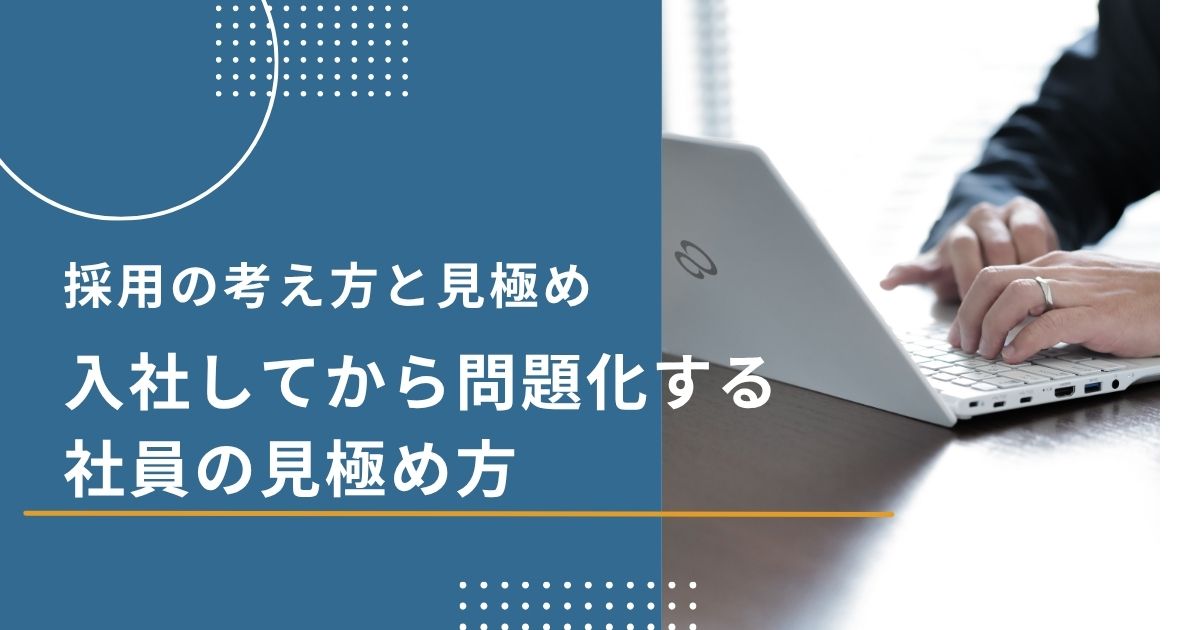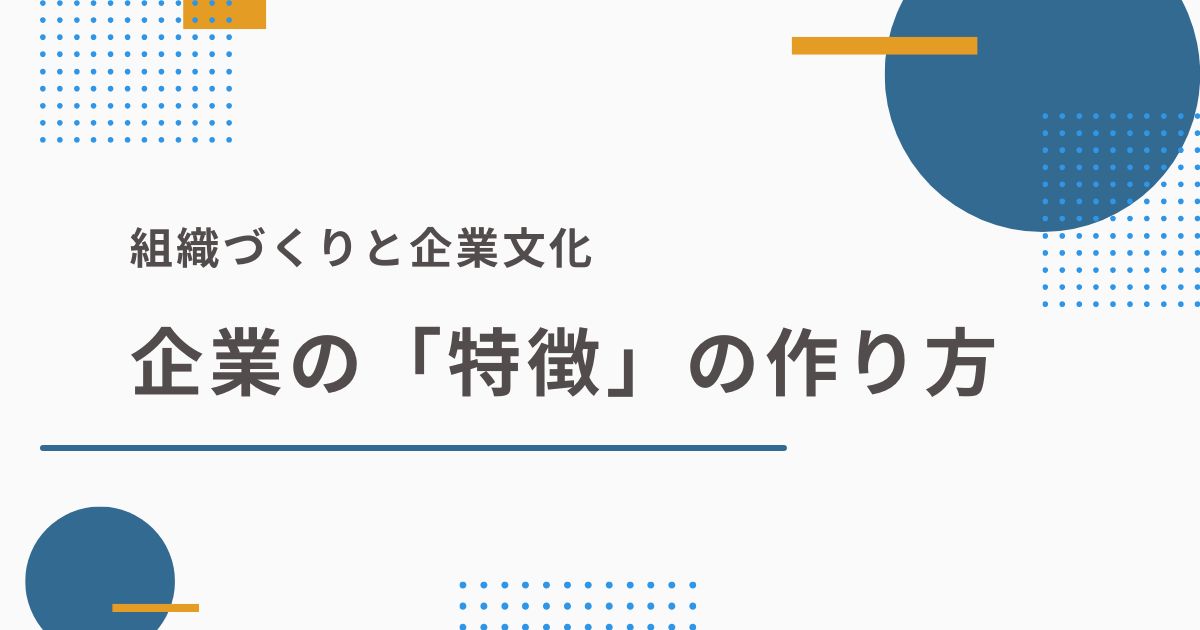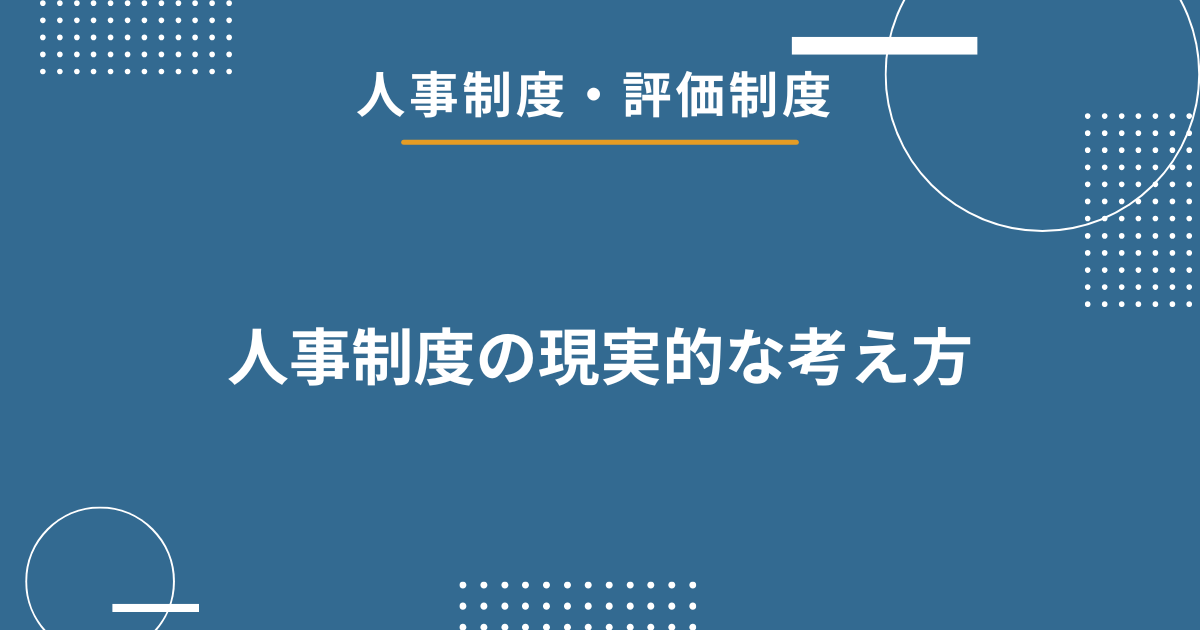もくじ
1. 強みと弱みの考え方
今日は私が考える、人事としての現実的な強みと弱みの考え方について書きます。
「強みを活かしましょう!」とはよく言われますよね。
この考え方、基本的に賛成です。
まず、強みと弱みを考えるにあたり、成果に大きくかかわってくるのは間違いなく強みの部分です。個の強みがどれだけ活かせるか。そして、それを組織としてどうやってチームとして機能させていけるか。
ただ、実際長年様々な組織を見ていて、上手く強みが発揮されず伸び悩むケースもありました。
それぞれの会社でも大きく期待していたのに・・・・なぜ・・・・???
と考え続けた中でわかったことがあります。
それは、「弱み」が目立ちすぎて「強み」が発揮される前段階でつまずいている、ということでした。
例えば「物事を改善していくのに的確で斬新なアイディアを生み出すことが強み」だったとします。
反面、「自分の都合で動きすぎ、会社のルールとしての書類を何度言っても出さず、定例ミーティングも出ず、頼んだこともやらないことが弱み」だとします。
結果、強みが発揮され「こんなことをやろう!」とアイディアを出しても、日ごろ弱みをたくさん目にしている職場としては、どうしても不信感を感じてしまい、アイディアが実行されにくくなるのです。
以前も書いたのですが、どうしても人間の防衛本能から、マイナスな面に着目してしまうのです。
だからと言って・・・・「弱みを強みに変えていこう!」という精神論もうまくいきません。
そもそも、強み・弱みというのはその方のもともと持っている能力や価値観からくる部分であり、あくまでも強みは強み、弱みは弱みであり、弱みを強みに変えていくことは、ほぼ不可能ではないでしょうか?少なくとも私自身でチャレンジしてみても出来ませんでした。
ですが、弱みをこのまま放置することは、強みが発揮されず組織としても個人としても「もったいない」状態になります。
だからこそ・・・・・現実的に強みを発揮してもらうためのステップとして、「弱みが最低限問題にならないレベル」までにしてもらうことも必要だと感じています。
評価制度の導入でも、「5段階評価で1⇒5にすることはほぼ無理ですが、1⇒2や3にするところまでは会社と本人次第で可能です」と伝えさせて頂きます。
そのうえで、「4や5をもっと強化していこう」という順番ですね。
もし仮に自分が評価会議などでアドバイスとしてお伝えするのであれば、
「書類は完成度高くなくてもいいから、最低限必要なことだけ書いて、ギリギリでいいから出してもらう」
「頼まれたことをやらない場合は、先に断るとか、やっていない場合は謝るとか頼んだ相手に何かしらの返事をする」
といって弱みの部分に対してMUSTのレベルを示すようにします。
そのうえで、「この○○というプロジェクトは強みを活かして、アイディア出して全力で取り組んで、結果を出して周囲に認めてもらう!」
というのが、現実的に力を発揮してもらう目標設定になると思います。
弱みを目立たなくする、というのはとても大事という話でした。