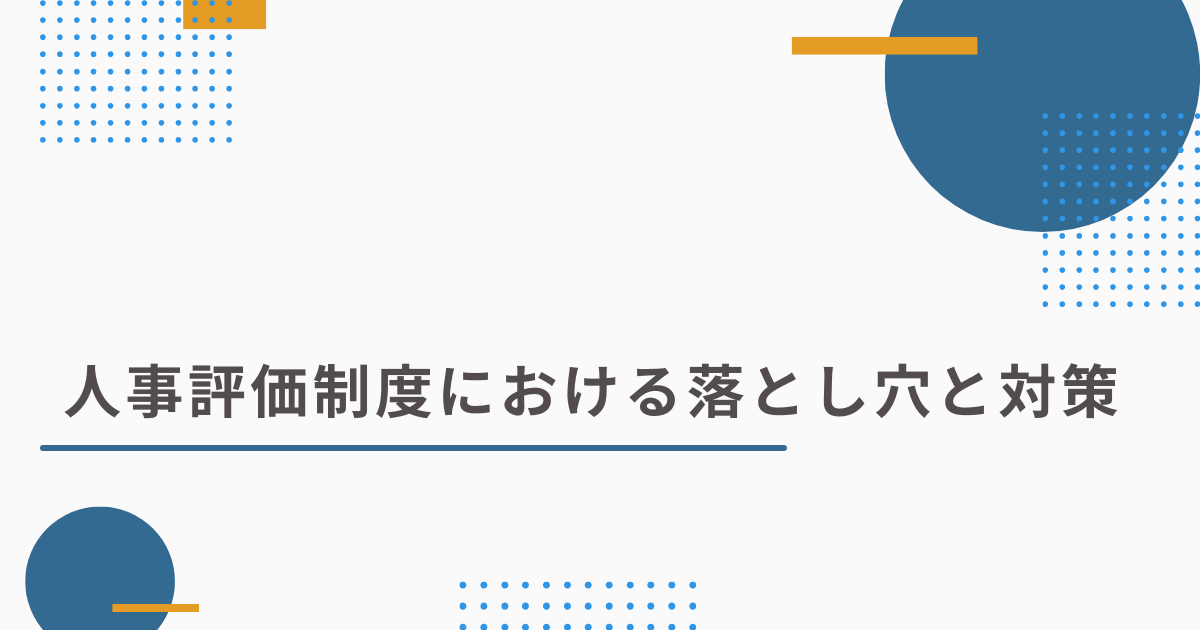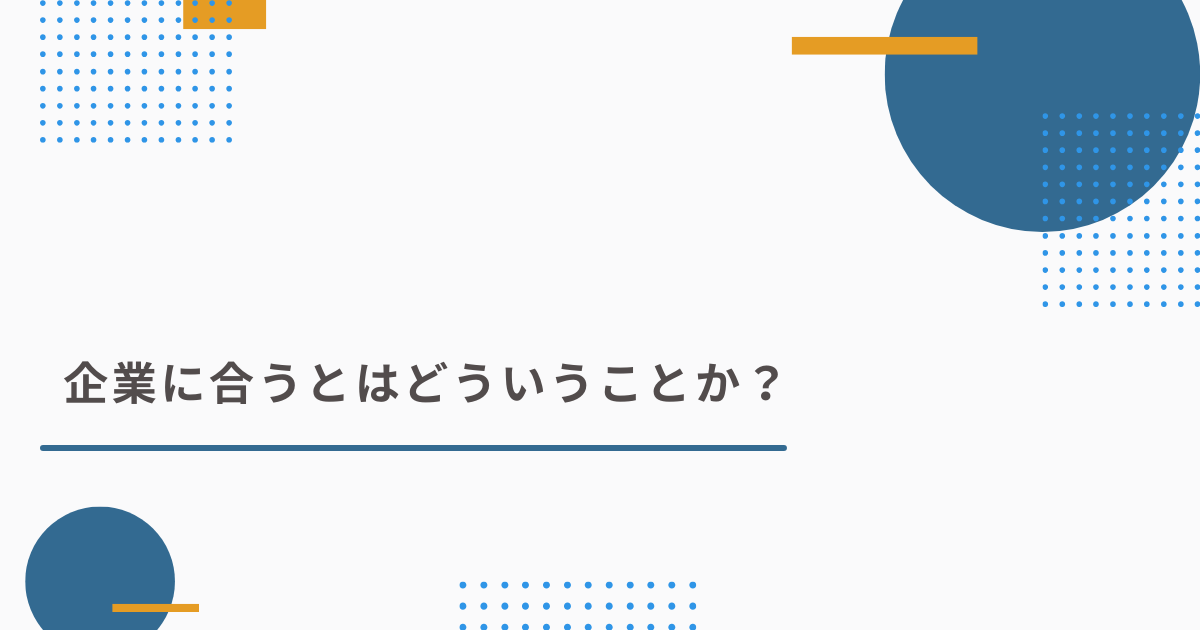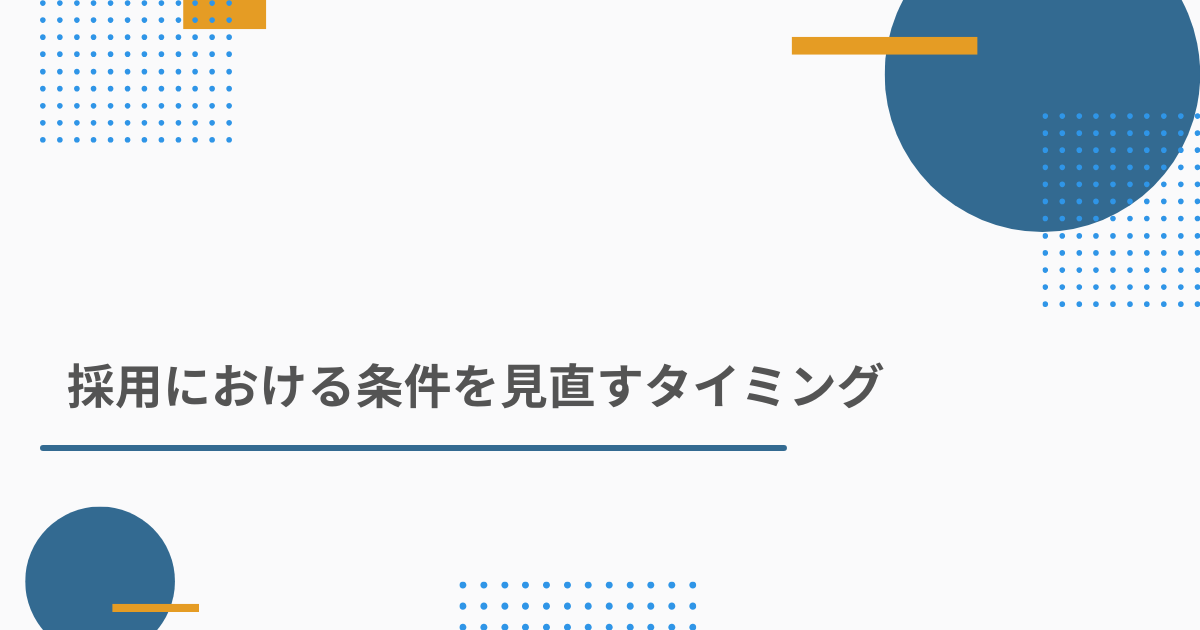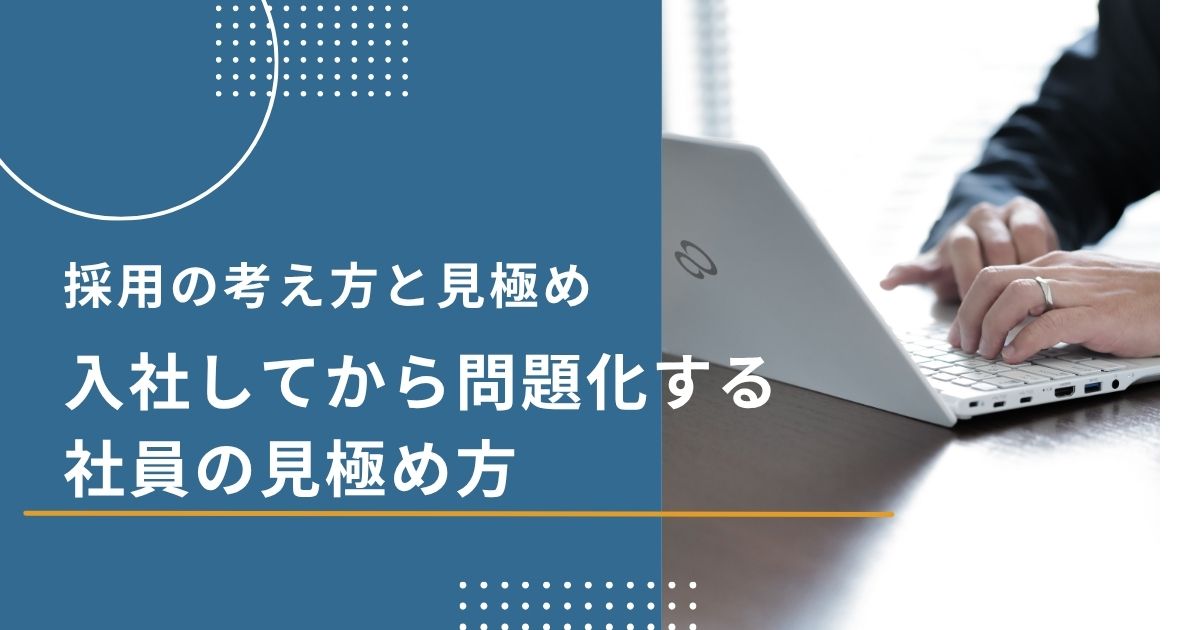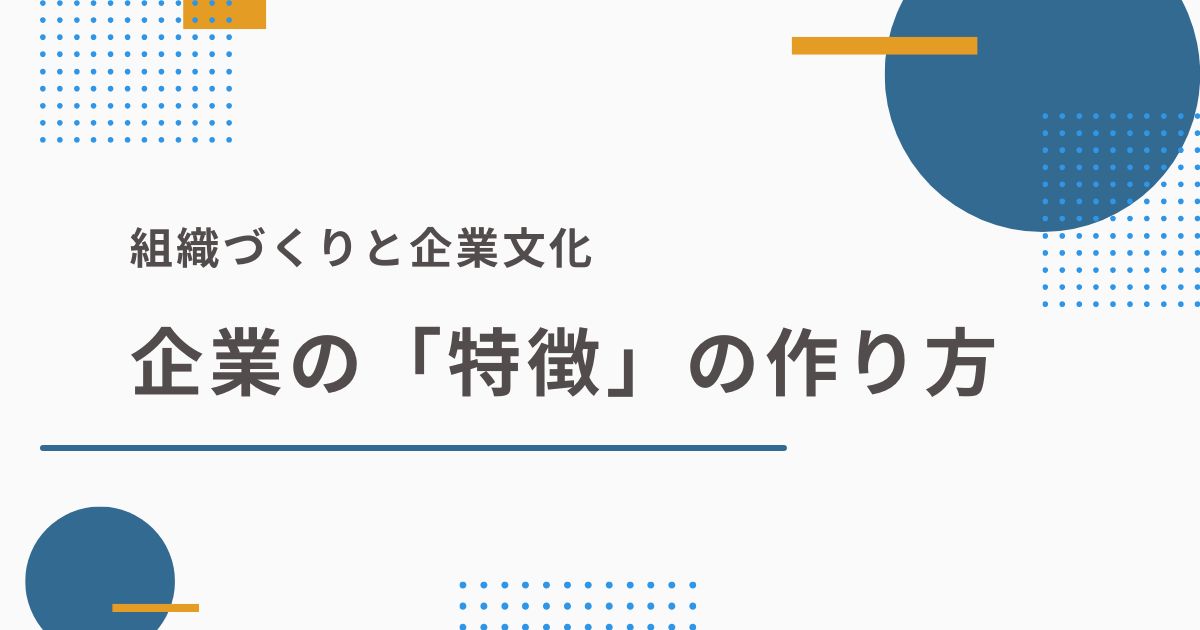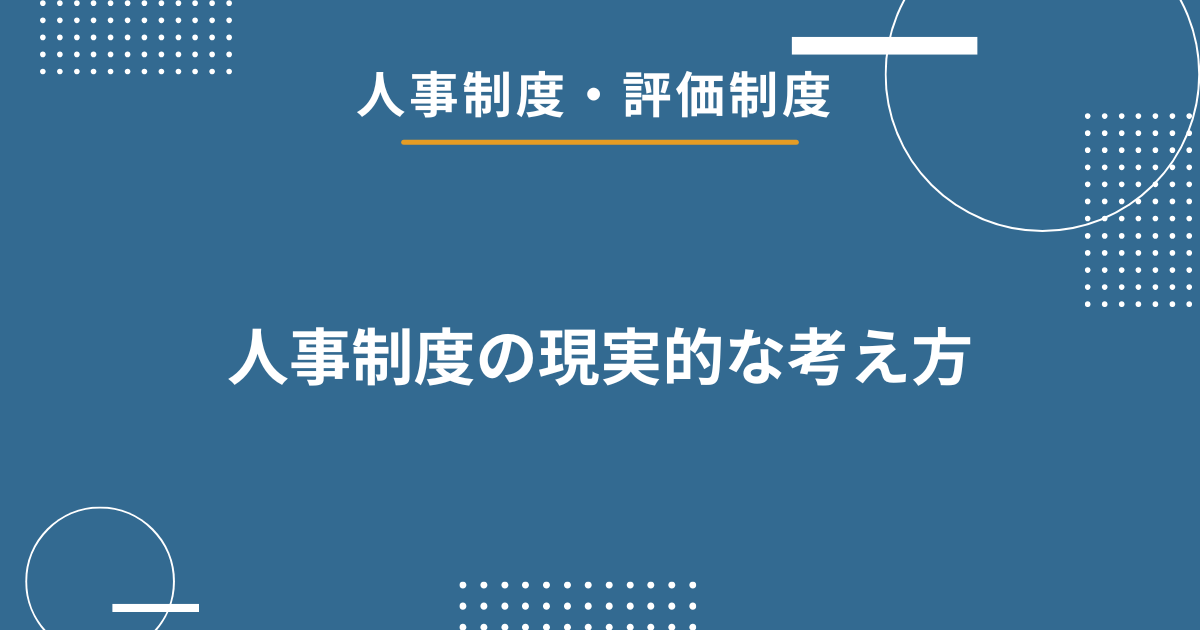1. 人事評価制度における落とし穴と対策
人事評価制度がうまく機能しない場合、問題点は大きく3つに分けられて
・評価制度そのものの問題
・運用の問題
・組織の問題
のいずれかであることが多いです。
今回は評価制度そのものの落とし穴について書きたいと思います。
通常、人事制度は社長や幹部の方の、「会社としてこう向かっていきたい」という理想を設定し、それに基づいて各項目を話し合いながら決めていくやり方が一般的です。そして、多くの場合、理性的にロジカルに作られるのですが、実はここが落とし穴で、問題が発生しやすいのです。
理性的にロジカルに作られた評価制度で評価を行った場合、最初は形としては問題なく立ち上がったかのように見えますが、段々と評価を行っていくうち、実際の評価と制度に乖離が発生していきます。
それは何故か。
多くの会社の評価会議に参加して痛感するのは、一部の評価能力が高い方を除き、ほとんどの評価者は「感情」→「評価」の順で評価をするからです。どういうことかというと、大体感情的に大まかな評価が決まり、そのあとはその感情に引っ張られつつ評価が決まっていくのです。
実際、評価者訓練などでは「感情」ではなく、根拠に基づいて理性的に評価を行うよう指導されます。制度もそれに合わせて作られます。
しかし、人間の感情の強さを考慮しないと、現実的に機能しない制度になってしまいます。
特に・・・・社長の意を組んで、理想に燃えた制度が作られるのは大変良いのですが、実際にその評価制度通りに最も評価しないのも、大体社長です。そして、制度運用に人事が戸惑い、現場にうまく落とし込めず、制度が上手く機能しなくなってしまうのです。
つまり、制度上、大事にしなければいけないのは、特に社長の「感情」です。ここで言う感情とは、実は社長自身も気づいていないことが多い、本能的に「好き」「嫌い」と思う部分です。例えば、良くあるケースとして、社長は「自由にどんどんやってくれ!」と口では言うのに、自分に許可なく自由にやっていると腹を立て、結局全部社長が決めるので、評価の高い人は「いかに社長の意の通りに実直に動けるか」だったりします。
そうやって人事制度を考えると、社長の感情に沿った制度になっていきますが、私はそれこそが自社に合った制度だと思っています。今まで、その感情に従って、組織を作ってきたのは社長さんとその社員の皆さんなのですから。それこそが、自社の正解だと思うのです。無理に一般論を持ち込むよりも、自分たちの道を強化していくことが、人事制度が機能する上でも大事なことだと考えています。
今まで、会社を育てて来た社長の想い、もっとリスペクトして制度を作るべきなのです。
ただし、社長に対して、普通に質問していくと、ほとんどの場合、どうしても綺麗ごとになってしまい、本音は出てきません。
では、弊社が制度構築を行う場合どうするか。
社長と弊社のみの空間(もしくは幹部の方で本当に腹心の一部の方も入ってもらう)で、社員一人一人について自由に話してもらうのです。といっても、ただ自由に話してもらうのではなく、弊社がガイドしながら、良いこと、悪いこと、そして今のポジションや仕事内容、給与、期待、失望などなどざっくばらんに話してもらうのです。当然、この内容は社員の方には伝えません(伝えられません!)。
ここで出てくる情報こそが血の通った評価の元となる会社の個性ともいうべき情報です。この工程を経ず、理想的な目標と打ち合わせで作られた制度には、どうしても会社の血の通った個性が生まれず、現実と乖離してしまいます。
そして、この情報をベースに制度として構築していくのです。つまり、多くの評価者が(特に社長は)「感情」→「評価」の順なので、制度もこの順番で作ると会社の個性が上手く入った制度になります。
こういうことを書くと、評価者訓練などを経て、理性的でフェアな制度運用が出来るようにすべきだ、という意見もお聞きするのですが、実体験から、人間の「感情」はとても強力で、採用基準から評価能力の高さにつながるような能力要件があり、それに基づいて採用されているような組織は別で、そういう組織はどのような制度を組んでもうまくいきます。そして、ほとんどの企業はそのような採用はしていないので、本能的な部分から目を背けず、制度に血を通わせた方が良いと思うのです。
実際、弊社が作らせて頂く制度は、感情を入れ込むことにエネルギィを割いていることが、失敗しない要因の一つになっています。
なお、近年海外ではAIが評価者をやる会社も出てきています。成果に重きを置く場合、このようなやり方も有りだと思いますし、今後増えていくでしょう。