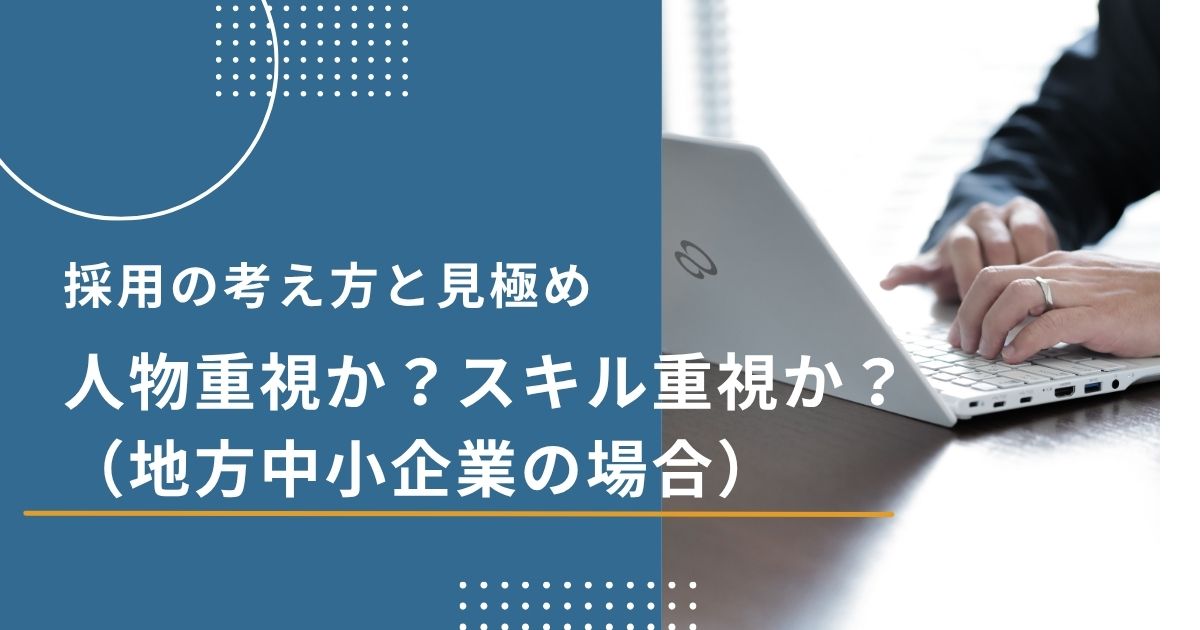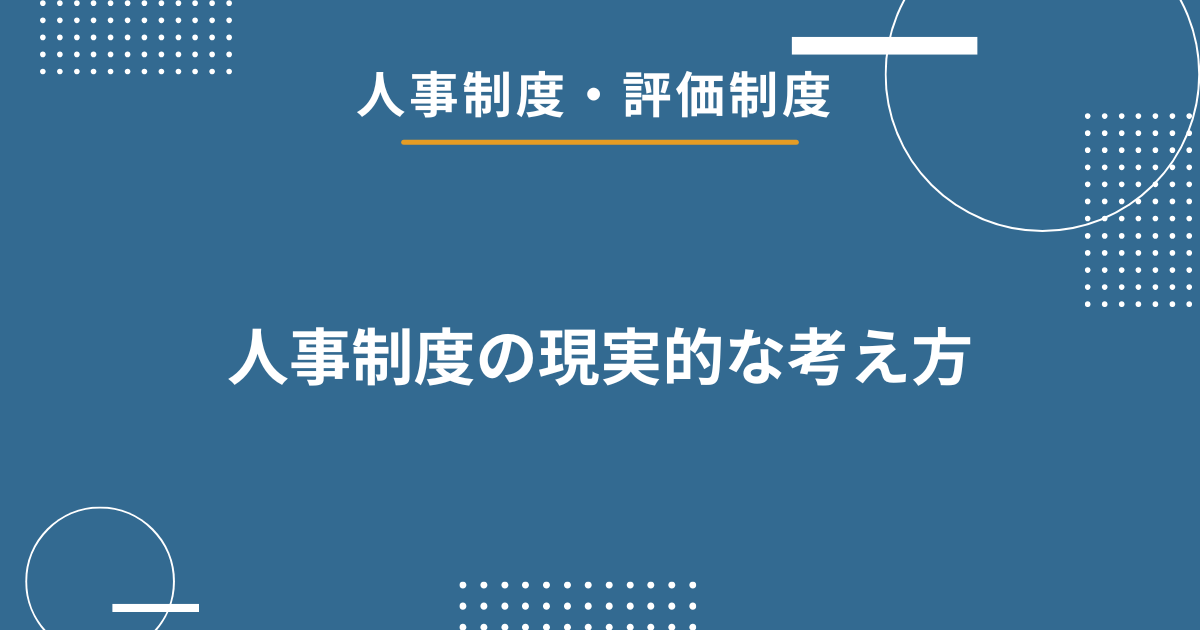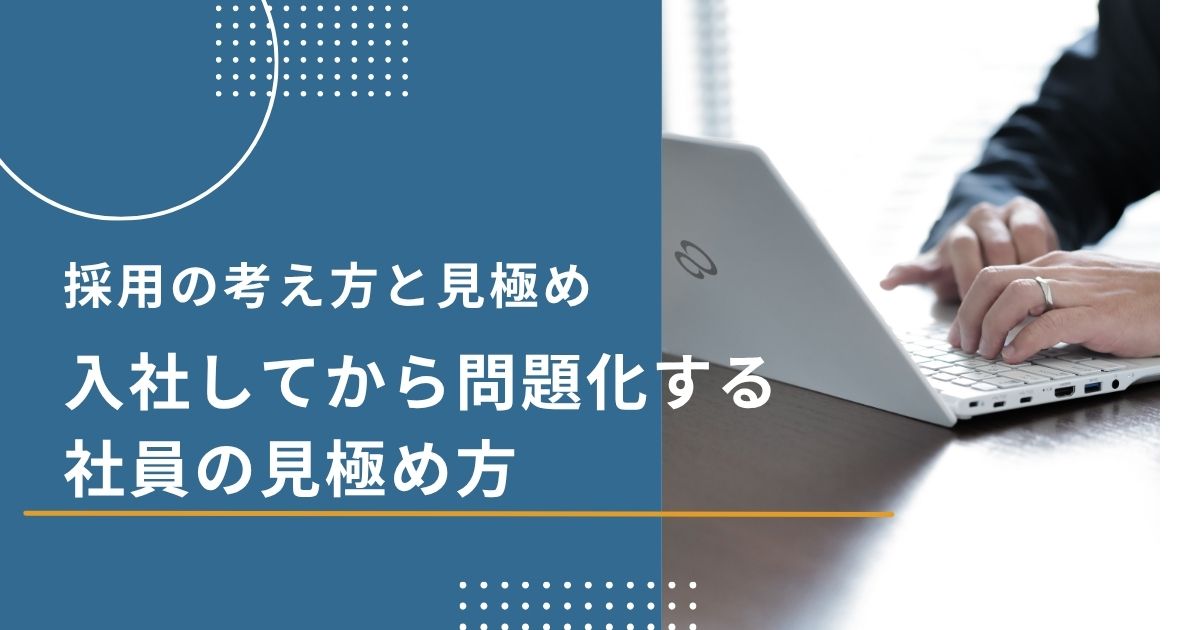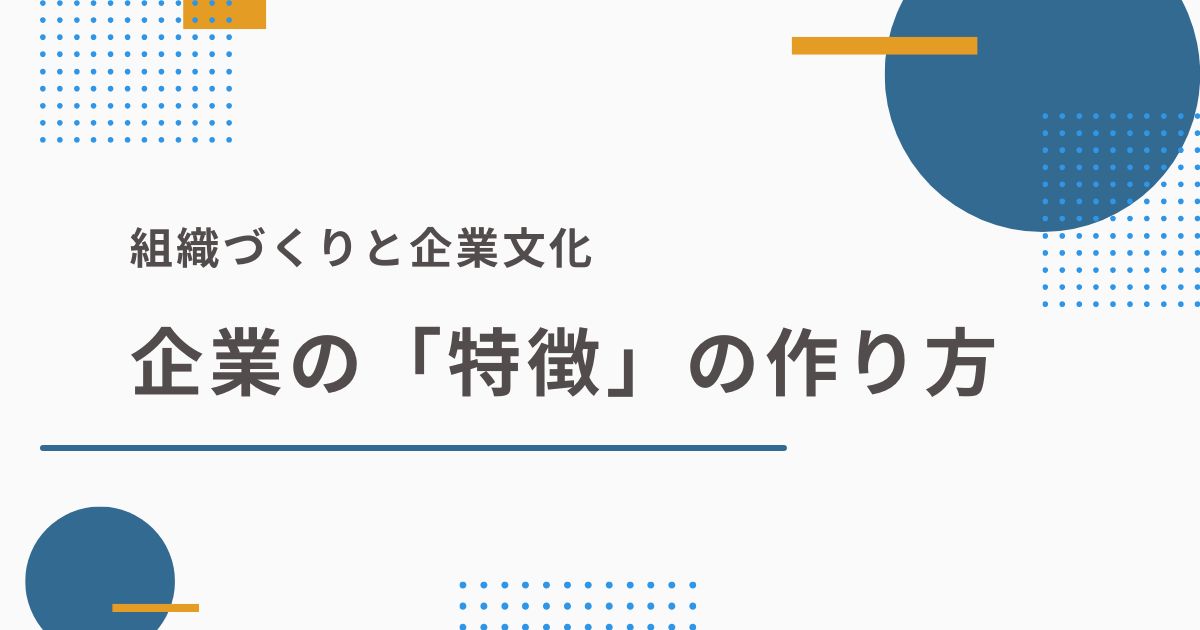1. スキル重視の採用は難しい
「人物重視」。ほとんどの企業が掲げる選考のうたい文句ですが、裏で話を聞くと、あのスキルが必要とか、あの資格が必要とか、学歴はこれくらいとか、理系出身じゃないと、とか、実は「スキル」面で採用が行われていることが多いです。
特に地方の中小企業になると、「地元の○○大学出身者で、理系○○の学部出身者が欲しい」と過去の採用実績から希望を上げるのですが、現実的に厳しいです。
計算してみましょう。
その○○大学の理系○○学部が何人いるか?例えば、80人だったとしましょう。
その中で、まず大手で研究・開発に流れていく学生が理系の場合5割だとする。
さらに地元や地方に残りたいと希望する学生が残ったうちの5割だとする。
そうすると、20人くらいがターゲットになるわけです。
ただし、この20人を地方数十社で取り合うので、自社に応募があるとすれば、多くて1~2人くらいあれば良い方。
そうすると質的に採用できない場合もあるし、競合した場合入社してもらえるかの問題もある。ということで、かなり採用は苦しい。
では、なぜこのようなことになるかというと、「スキル」面で選考基準を組み立てると、大手も中小も他社も似たような基準になってしまうからです。もちろん、似た基準でもいいから、うちはベストを取りに行く!という考えは素晴らしいと思いますが、やはり現実は厳しく立ちはだかります。
ですから、スキル面ではなく、言葉通り「人物重視」で採用をすることが、競合を減らすために大事なことなのです。もちろん本質的な定着を見るうえでもとてもとても大事なことです。
2. なぜ「人物重視」がうまく拡がらないのか?
では、なぜ「人物重視」がうまく拡がらないのか?
これは、「人を見る」技術の不足だと思います。もっというと、見る側の思考不足です。
人を見るためには、あの手この手で見ていく必要がありますが、その中で大事なことは、しっかりその人の人物像を概念的に構築していくことです。
例えば、
- 書類の字が雑
- 服装が乱れている
- 言葉遣いがラフ
などがあれば、「おおざっぱで細かいことには無頓着」となるから、細かい事務仕事や定型業務などは向かない可能性が高いです。
ただし、そのうえで
- 話している内容は無駄がなく本質的 ・新しいことを吸収するのが好き
- アイディアが出せる
という傾向が加われば、「前進する改革は得意」という側面が出てきます。ちょっと良さそうだ、と思ったりします。
加えて、
- 他人の話はあまり受け入れない
- 自分の興味に忠実
- 自分の意見が通らないとやる気がなくなる
という傾向が加わり、「わがまま」という側面が出てくるとどうでしょう。
採用するのは難しいかも、となりますよね。
まとめると、1匹狼でどんどん好きなことができて結果が出ればいい、という場には良いかもしれませんが、普通の組織として受け入れるにはリスクが大きすぎる可能性が高い人物像なのです。特に地方の中小企業だと、オーナーの手に負えなくなって組織を壊されるリスクがあるので、採用は避けたほうが良いですね。
3. だから、人物像を重視して、選考に力を入れる
このように選考過程で分析的に人物像を作っていけばよいのですが、思考を伴う作業のため、精度よく行うのは結構難しいです。もっというと、人を見ていく作業を放棄している会社さんも多くて、「人はわからん」と開き直っていて、もったいないな、と思うのです。
そして、わかりやすく、思考を必要としない「スキル面」を見てしまい、レッドオーシャンになって、採用できたとしても、過去の経験はあるけれど、自社のやり方に慣れてくれず組織に馴染まない・・・・みたいになってしまうのです。
逆に、しっかり人物重視の採用を行っていくと、他社さんが目をつけなかった逸材を採用することが出来、何年か後の会社の中核になっていくケースをたくさん見てきました。
人物重視の採用は難しく、エネルギーを必要とします。だからこそ、出会える逸材がいるのです。